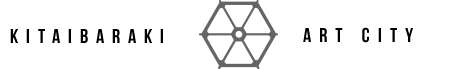作家
陶芸家
田中荘弐
象嵌(ぞうがん)という言葉を聞いたことがあるだろうか。 象は「かたどる」嵌は「はめる」という意味を持ち、一つの素材に異質の素材を嵌め込むという工芸技法のひとつである。 この地で生まれ育ち、かれこれ30年近く象嵌技法を取り入れた作品を数多く作ってらっしゃる 陶芸家の田中荘弐(そうじ)さん。 初めて工房兼ギャラリーにお邪魔した時、ご自身の繊細な美意識と独自の象嵌技法によって成り立つ作品に圧倒されてしまった。

聞けば、田中さんの5代前の祖先が京都から益子に陶芸の技術指導者として招かれたという家柄。 しかし特に血縁の中で陶芸を教わったということでもなければ、家業ということでもなかったとのこと。だが、田中さんが選んだ道は陶芸家としての道。



「僕は陶芸にまつわる、あらゆる技法を試しました。その中で、食べていくには人と違うことをやらなければ食べていけないと思ったんですね。ですので、一般的には難しいとされている陶器の中に磁器を埋め込む象嵌技法というものに辿り着きました。」「わたしは花や植物が好きで、それを仕事に活かせたら好きなんだから集中出来るだろうと思い、それで身近な山野草を描くようになりました。ですが、陶器の上に絵を描いたのでは釜に入れた時に炭化して消えてしまうんですね。磁器の場合はそれがない。なのでより味わい深くそれらを表現するには、どうしても磁器を象嵌する必要があったということです。」表層的に磁器を薄く象嵌することは比較的あることらしいのだが、田中さんは失敗するリスクを飛び越え、深く磁器を象嵌する。それが田中さんの作品が持つ固有の美を浮かび上がらせる。





磁器を象嵌し表現される山野草が作品の主役であるならば、陶器の部分はその背景である。 たかが背景と言えど、田中さんの作品が持つ味わい深いコントラストを生むために非常に重要な要素である。この原料である土が、高温で焼くことにも耐え、独特の風味を出すことが可能な地元で採れる蛙目(がいろめ)粘土なのだそう。作品の背景を構成する材料に地元の土が使われ、身近な山野草が田中さんが長年研磨されてきた象嵌技法によって表現される。まさにここにしかない、この場所が生んだ芸術作品であろうと思う。